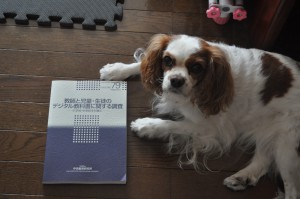毎年、夏に開催している「学校社会学研究会」も31回目を迎えます。今年は、放送大学のセミナーハウス(千葉幕張)の講義室で開催します。
日時 2013年8月19日(月)~20日(火)
場所 放送大学セミナーハウス・会議室 (千葉・幕張)
〒261-8586 千葉県千葉市美浜区若葉2−11 043-276-5111
(参加費500円、懇親会費4000円 <予定>)
8月19日 (月)
受付 10時15分~10時30分
10時30分~11時40分
森 俊英(元石巻市立蛇田中学校長)
「東北大震災と公立小・中学校の果たす役割」
11時40分~12時20分
阿部智美(中央大学大学院) 「エリート系高校生の抱く『学校観』」
12時20分~13時30分 昼食 (各自)
13時30分~ 14時30分
浜島幸司(立教大学)、谷田川ルミ(芝浦工大)
「デジタル教科書に対する教師と児童・生徒の意識-調査結果の要約とデータの再分析-」
14時30分~15時10分
藤田里菜 (能美市立寺井中学校)
「:学校現場で感じる違和感―:教師から生徒への関わりにおいてー
15時20分~16時20分
野崎与志子 (ニューヨーク州立大学、上智大学非常勤)
「アメリカ合衆国の高等教育とジェンダー」
16時20分~17時20分
小針誠 (同志社女子大学)
「イギリスのPrep Schoolとエリート教育」
17時20分~18時40分
鷲北貴史(元、LEC大学進路支援センター長。高崎経済大)
児玉英明(京都府立大)
「教育困難校における実践の蓄積と共有~低意欲学生を対象とした教育開発という先端領域~」
19時分~21時分 懇親会 (場所未定)
8月20日(火曜日)
9時30分~10時30分
白石義郎(久留米大学)
「学校創生期におけるスポーツの学校化:森有礼の二人の弟子」
10時30分~11時30分
井口博充 (放送大学講師)
「アメリカの若者と情報デバイスとポリティックス」
11時30分~12時30分
山本雄二 (関西大学)
「『ぴったりブルマー』はいかにして中学校を席巻したのか――ブルマーの謎 その2」
12時30分~12時40分 総会
12時45分 解散
世話役 岡崎友典(放送大学)、
武内清(敬愛大学)ー問い合わせ先 fwne3137@mb.infoweb.ne.jp
デジタル教科書に関する調査
公益財団法人「中央教育研究所」の研究報告79号『教師と児童・生徒のデジタル教科書に関する調査』が、5月に発刊された。
我々のメンバー14名が、2年近くかけて調査票を練り、実施した調査の報告書である。是非お読みいただきたい。
(中央教育研究所)(http://www.chu-ken.jp/pdf/kanko79.pdf)
。
内外教育にも、内容が紹介された.
IMG
大学の授業の参観
今週は、敬愛大学では、FDの一貫で、他の先生の授業を参観する週になっていた。昨日(5日)、それぞれ短時間だったが、4つの授業を見学させていただいた。他の先生の授業を見学すると、自分で教壇に立っている時にはわからないことがいくつか見えてくる。以下、その感想。
① それぞれの先生は、それぞれの授業スタイルで、一生懸命に授業をしている。ほとんどの教員はプリントを配り、板書をしながら、わかりやすい説明をしている。抽象的な内容も、身近な例を引き、学生の興味を引く工夫をしている。映像でリアリティを出す先生もいる。実技の授業もある。
② 先生たちの熱意や思いが、学生に伝わっているかと言うと、必ずしもそうとは言えない。どの授業も私語はなく、静かであったが、前の方に座り熱心に聞く学生もいるが、後ろの席に座り、肘を枕に寝ている学生や携帯をいじっている学生も、授業によっては少なからずいる。
③ 学生に話しかけるように講義する先生の授業は、好評のようで、多くの学生が顔を上げ、熱心に聞いている。実技の授業も皆楽しそうである。大学の講義らしく、先生がアカデミックな内容を、学生の受講態度に関わりなく、一方的に話す授業は、学生が顔を上げている率が低く、全く聞いていない学生もかなりみられる(私の授業はこれに近いかもしれない)。
④ 一つの授業で、リーダーシップのタイプの講義があり、「仕事志向」と「人間志向」で、リーダーシップのタイプが4タイプできるという説明があった。さらにどのタイプが有効かは、フォロワーの「成熟度」によるという説明があった。これから言うと、学生の成熟度により、どのようなスタイルの授業が有効化かが、決まると思った。
⑤ 学生達は、授業の内容以上に、先生(講義者)が自分達にどの程度関心を示し、向き合ってくれるのかということも期待しているらしいことが感じられた(それだけ、今の大学生は幼く、生徒化している)。
講義を聞かないで、携帯をいじっている学生や、寝ている学生に対しては、(怒りを感じながら)その存在を無視して、授業をすすめる大学教師が、一般的には多い(私もそうだと思う)。 ところが、学生からすると、見捨てられ、無視された、さびしさも感じているのではないかと思った。今度、学生の感想も聞いてみたい。
⑥ 1時間半の授業は、聞く方からすると、かなり長く感じた。
関西学院大学での日本子ども社会学会開催
正統と異端
卒業生のS氏より、学生文化に関する興味ぶかいコメントをいただいた。感謝。
(下記)
<文化論ではメインカルチャーがあってサブカルチャーの存在が認めらるという構図があると思います。
だとするなら、学生文化というサブカルチャーにあっても、その中を分ければ、真面目というメインカルチャーと不真面目というサブカルチャーが存在し、通常はメインカルチャーが一定の存在感を明示するが、時期によっては、サブカルチャーとしての不真面目な学生文化が顕在化し、反対にある時期には通常以上にメインカルチャーである真面目な側面が強調されて顕在化する。つまり、学生文化の不真面目な側面というのは、学生文化のサブカルチャーとしての地位しか持たない。不真面目な学生文化は異端なのではないでしょうか。
異端が正当な学問の追究者から通常の能力評価と異なる評価を得ることは、それがプラスである場合、理解できない謎とならざるを得ないと思います。なぜなら、それが異端であるということ示すものでもあるからです。
このような学生文化論は学生が増えてユニバーサル化するにしたがって階層化し、大学の序列化が一層進むように思われるのに、旧帝大は疲弊し、新規大学の新設が衰えないのはどういうことなのだろう。
大学の学生文化は大学の既存の文化とは一致しないものなのであろうか。就職という時に威力を発揮していると思われるイメージとしての大学固有の文化は今の学生文化から隔たりがあるのか?
大学の学生文化を捉えるのは容易ではないようです>
是非、異端と正統という図式で考えてみたいと思った。同時に、以前に書いた次の文章を思い出した。
「学生文化」(サブカルチャー)は、大学文化(トータルカルチャー)との関連で、それへの適合、葛藤,反抗などを起こしつつ、発生、消滅していく存在であり、学生の成長、生活に多大な影響を与えている」(武内清編『キャンパスライフの今』玉川大学出版部,2003年、169頁)*。
*この本は、9名の研究仲間と書いたとてもいい本(装丁も素敵)だと思うが、今アマゾンで安く売っている。世の中の人は本の価値がわからないのか。
(http://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/4472302764/ref=sr_1_1_olp?ie=UTF8&qid=1372368898&sr=8-1&keywords=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%81%AE%E4%BB%8A&condition=used)