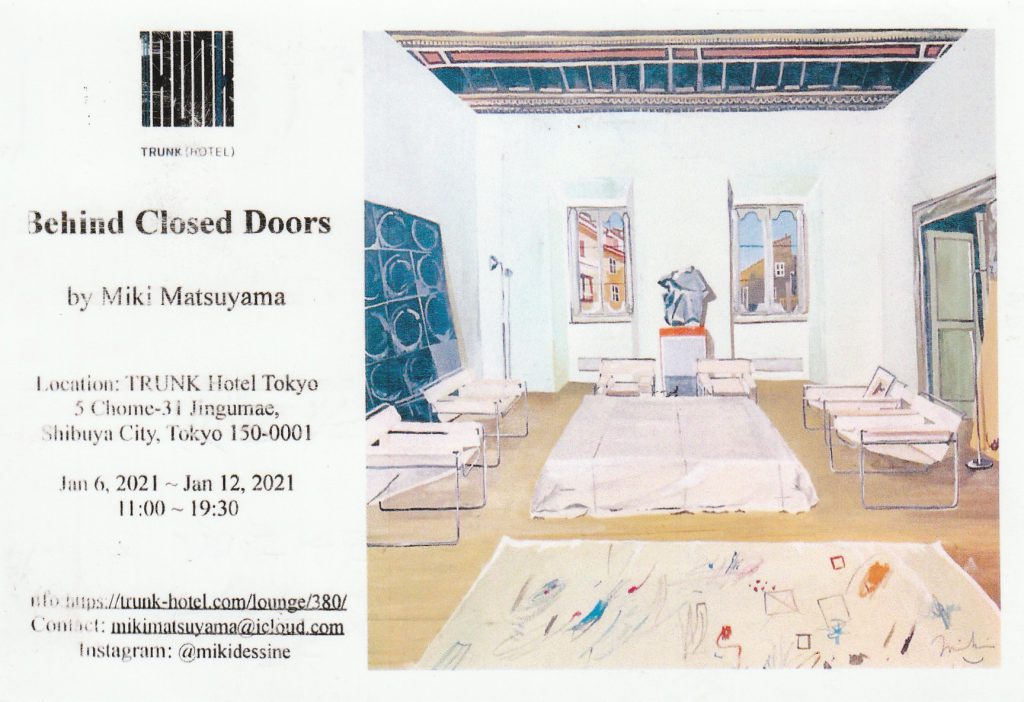寝る前にテレビのチャンネルを付けると意外にいい番組に出くわすことがある。昨日(12月29日)、NHKの総合で、「コクリコ坂から」制作に挑む親子の物語をもう一度!(2011年8月初回放送)」を見た。
<2人の人物の絆を描くドキュメンタリー「ふたり」。今回は映画監督・宮崎駿さんとその長男・吾朗さん。2011年公開「コクリコ坂から」は吾朗さんが監督、駿さんが脚本を担当。二人の合作ともいえる作品だ。しかし二人の間には知られざる葛藤があった。70歳にしてなお映画への情熱をたぎらせる父。偉大な父と比較される宿命を負いながらも、挑戦を続ける息子。衝突しながらも同じ目標に向かい情熱を燃やす父と子の物語>である。
宮崎駿のアニメ映画やジブリの映画は好きでこれまでほとんど見てきたように思う。宮崎吾郎の「ゲド戦記」はあまり評判がよくなかったが、見た印象は悪くなかった記憶がある。「コクリコ坂から」は好印象が残っているアニメだが、宮崎吾郎監督の映画とは失念していた。(この映画は、小5の姪と一緒に見に行って、最後のところの筋を姪から教えられたことを覚えている。)父と息子の葛藤というのは自分では経験していないので、あまり感じることはないが、「りっぱな父親を持つと大変」ということはわかる。
歴代興行収入ランキング」(http://www.eiga-ranking.com/boxoffice/japan/alltime/total)を見ると、最近まで、「千と千尋の神隠し」が1位で、50位までに6作品(「ハウルの動く城」6位、「もののけ姫」(7位)、「崖の上のポニョ」(12位)、「風たちぬ」(22位)、「仮ぐらしのアリエッティ」(42位)が上がっている。その他に「風の谷のナウシカ」「トトロ」「魔女の宅急便」他、印象に残っている作品も多いので、宮崎駿、ジブリの映画・アニメの凄さがわかる。
ただ、少し前に新海誠監督のアニメ映画「君の名は」(2016年)、「天気の子」(2019年)を見た時、その画像の新鮮さに驚き、その観点からみると宮崎駿の映像がその色彩も含めて、1時代前の古めかしいものに見えてしまった。
今日(30日)のNHK総合21時30分から、宮崎駿、監督・宮崎吾朗によるジブリ最新作「アーヤと魔女」が放映されるというが、どのようなものに仕上がっているのか。また、最近「千と千尋の神隠し」の興行成績を抜いて1位になった「鬼滅の刃」の映像は、どのようなものなのであろうか。いろいろ自分の目でも確かめてみたい。